こんにちは。しんしん心理研究所の心理師Shingo(しんしん)です。
「やる気が出ない」
「三日坊主で終わってしまう」
「最初は頑張れるのに、続かない」
そんなことを感じることはありませんか?
やる気がある状態は理想的ですが、実際にはその状態を維持し続けることはとても難しいものです。毎日の仕事や勉強、家事、人間関係の中で、私たちはさまざまなストレスにさらされています。そうした中で「やる気を保つ」というのは、決して簡単なことではありません。
モチベーション(動機づけ)は、私たちの行動を支える原動力であり、目標に向かって進むためのエネルギー源でもあります。しかし、そのエネルギーは無限ではなく、気分や体調、周囲の環境に左右され、浮き沈みがあります。そのため、モチベーションを自然と持続させるには、「ちょっとした工夫」が必要不可欠です。
今回の記事では、心理学的な知見や行動科学の考え方も交えながら、やる気を上手に保ち、目標達成へと近づくための「モチベーションを保つコツ」を7つ厳選してご紹介します。日々の暮らしに取り入れやすいシンプルな工夫ばかりなので、ぜひ気軽に試してみてください。
1.目的を明確にする(“なぜ”を掘り下げる)
何かを始めるとき、一番最初に大切なのは「目的=なぜそれをやるのか?」を明確にすることです。
たとえば、「英語を勉強したい」と思っても、「なぜ?」が曖昧だと、モチベーションはすぐに下がります。しかし、「海外旅行で現地の人と自由に話したい」「将来、海外の会社で働きたい」といった目的があると、自然とやる気が湧いてきます。
この「なぜ」の部分は、心理学では「内発的動機づけ」と呼ばれ、自分の内側から湧き上がる動機が強いほど、モチベーションは持続しやすいとされています。
自分の「なぜ」を紙に書き出して見える化してみましょう。
2.小さな目標に分ける(スモールステップ)
「ダイエットで5キロ痩せる」「資格試験に合格する」など、大きな目標はやる気の源にもなりますが、一方で「ゴールが遠すぎる」と感じてしまうと、逆にやる気を失ってしまいます。
そんなときは、大きな目標を「小さな目標」に分解しましょう。これを「スモールステップの原則」と言います。
- 「1日10分ウォーキングする」
- 「毎日、単語を5個覚える」
こうした小さな達成体験を積み重ねることで、「自分はできる」という自己効力感が育ち、やる気を継続しやすくなります。
3.記録をつける(行動の見える化)
毎日、自分がどんな行動をしたかを記録する習慣も、モチベーション維持に効果的です。
- 日記
- チェックリスト
- 習慣化アプリ
などを使って、「今日もできた!」という実感を得ることが大切です。
心理学の行動理論でも、「達成感」と「可視化」は行動の継続に直結するとされています。たとえ小さな行動でも、「やった証拠」が残ると、脳はそれをポジティブに捉え、次も頑張ろうという気持ちになります。
4.「できた自分」を褒める(自己肯定感を育てる)
モチベーションを保つためには、「自分を褒める」ことがとても重要です。
日本人は謙遜の文化もあり、「これぐらい当たり前」「まだまだ足りない」と思いがちですが、それではやる気は長続きしません。むしろ、「昨日より10分長く勉強できた」「今日は一歩踏み出せた」など、「できたことに目を向けて自分を肯定する習慣」が、やる気を後押しします。
心理学ではこれを「自己肯定感」と呼び、自己肯定感が高い人ほど、挑戦し続ける力が強いと言われています。
5.環境を整える(やる気が出る仕組みをつくる)
やる気は「気合」だけでは続きません。むしろ、環境の影響が大きいのです。
- 勉強する机の上を片付ける
- スマホを手の届かない場所に置く
- カフェなど集中できる場所に行く
など、やる気が出る「環境づくり」を意識しましょう。
人は意思の力よりも、環境によって行動が左右されやすい生き物です。自分が自然と頑張れるような場所、仕組みを整えることが、モチベーション維持の第一歩です。
6.人とつながる(社会的な動機づけ)
ひとりで頑張ろうとすると、孤独や不安からやる気が途切れやすくなります。そんなときは、誰かと一緒に取り組む、応援してもらうことが効果的です。
- 友人と一緒にダイエットに挑戦する
- SNSで進捗を共有する
- コーチやメンターに相談する
など、他者とのつながりがモチベーションを支えることは、心理学的にも「社会的動機づけ」として知られています。誰かに見守ってもらっているだけでも、やる気が高まりやすくなります。
7.「やる気が出ない日があってもOK」と考える(完璧主義を手放す)
最後に、最も大切なことをお伝えします。
それは、「やる気が出ない日があっても、当たり前」だということ。人間は感情の波がある生き物です。常にモチベーションが高い状態を維持することは不可能です。
だからこそ、完璧を目指さず、「7割くらいの力でOK」という気持ちで続けることが大切です。
心理学でも、「自己受容」が高い人ほど、ストレスに強く、モチベーションの回復も早いことが分かっています。
まとめ
モチベーションは「湧いてくるもの」ではなく、「整えるもの」「管理するもの」です。気分が乗るのを待つのではなく、自分自身の行動や環境を工夫することで、意識的にモチベーションを育てていくことが可能です。毎日の習慣や生活リズム、働く環境、人との関係性など、様々な要因によってモチベーションは大きく左右されます。さらに、食事や睡眠、運動などの身体的な要素も、やる気に密接に関係していることが多いため、生活全体を見直すことも大切です。
今回ご紹介した7つのコツは、どれも特別な道具や能力を必要とするものではなく、ちょっとした意識の変化と日々の積み重ねで実践できるものばかりです。すぐにすべてを完璧に行う必要はありません。まずは一つでも、あなたの生活に取り入れてみることから始めてみてください。その一歩が、あなたの毎日をより充実させ、モチベーションの安定につながっていくはずです。
モチベーションは、誰にでも波があります。でも、ちょっとしたコツで「続けられる自分」に変わることができます。焦らず、自分のペースで進んでいきましょう。
なかなか自己肯定感が高められないとお悩みの方は、しんしん心理研究所の「繊細さんの自己肯定感を上げるカウンセリング」を活用してみて下さい。
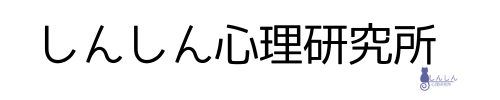



コメント