こんにちは。しんしん心理研究所の心理師Shingp(しんしん)です。今回は日本の福祉の考え方をベースに、困難な状況からリカバリーするためのヒントをまとめてみます。
日本の福祉制度は長い歴史があり、時代とともに変わってきました。その中で「自助・共助・公助」という考え方が、福祉や立ち直りの大事なポイントとして広く知られています。この三つの要素は、困難な状況から立ち直り、より良い生活を築くための基本的な枠組みです。この記事では、日本の福祉の現状と、それぞれの要素を使ったリカバリーのヒントを紹介します。
「自助」 自分で自分を助ける力
「自助」は、自分自身で問題を解決するために頑張ることを意味します。日本では自己責任がよく強調され、自分でできることから始めることが大事だとされています。しかし「自助」はただ自己責任を押し付けるものではなく、自分を見つめ直し、成長していく過程でもあります。
例えば、生活の中でストレスを感じたとき、マインドフルネスや深呼吸をしたり日記を書いたりすることは「自助」の一つです。また、自分の気持ちや状況を理解し、何が必要かを考えることも大切です。最近では、スマートフォンのアプリを使ってメンタルヘルスを管理する方法も増えており、そうした技術を使うことも「自助」の一部として考えられます。
セルフケアは、自分の心と体の健康を保つための大事な手段です。例えば、定期的な運動やバランスの取れた食事も「自助」の一環です。健康的な生活習慣を持つことで、ストレスに対する耐性が強くなり、困難な状況でも前向きに取り組む力を得ることができます。また、自分を褒めることや、ポジティブな思考を持つこともセルフケアの一つです。小さな成功を認めることで、自己肯定感を高め、さらに成長するための原動力になります。
「共助」 支え合うコミュニティの力
「共助」は、家族や友達、地域社会などの周りの人と助け合うことです。現代では孤立が問題になることが多く、共助の重要性はどんどん高まっています。人とのつながりは、困ったときに立ち直る大きな力になります。
例えば、近所の人たちと交流しながら、日常的に支え合う関係を作ることが考えられます。また、地域のボランティア活動に参加することも「共助」の一つです。助け合うことは、困っている人を助けるだけでなく、助ける側も充実感やつながりを感じることができ、自分自身のリカバリーにもつながります。
家族や友達との絆は、心の支えになるだけでなく、実際に助け合うことで困難を乗り越える力となります。例えば、家族が困っているときにサポートすることで、家族全体の結束力が強まり、安心感を感じることができます。また、友達と一緒に楽しむ時間を持つことも大切です。笑顔や楽しい時間は、ストレスを軽減し、心の健康を保つための大切な要素です。
特に、災害時には地域の共助が大きな役割を果たします。日本は自然災害が多い国で、そのたびに地域の人たちが協力して助け合う姿が見られます。そうした共助の精神を日常でも続けることが、福祉の基盤になります。日常生活でも、困っている人に手を差し伸べることで、地域全体のつながりが強くなります。共助の精神は、個人だけでなく社会全体の強さを作り上げる重要な要素です。
「公助」 社会制度としての福祉
「公助」は、政府や自治体が提供する公的な支援のことです。日本の福祉制度には、医療保険、年金、生活保護など、多くの公的サービスがあり、特に困っている人を支える大事な役割を果たしています。「公助」は、自助や共助だけでは足りない部分を補い、誰もが安心して生活できる社会を目指しています。
しかし、日本の福祉制度には課題もあります。例えば、高齢化が進んで福祉にかかるお金が増えていたり、制度が複雑で必要な人が利用しにくいという問題があります。こうした課題に対しては、制度の改善を求める声を上げることや、自分に合った支援を正しく理解することが大事です。福祉制度をもっと使いやすくするためには、情報提供の仕方や手続きの簡略化などが求められています。
公的支援を受けることに抵抗を感じる人もいますが、これは社会の仕組みとして設けられたものであり、必要なときに利用することは当然の権利です。例えば、生活が苦しくなったときに生活保護を申請することや、心の問題で困っているときにカウンセリングを受けることは、公助の一部として大切です。公助を活用することで、自分の生活を安定させ、次のステップに進むための基盤を作ることができます。
リカバリーのためのヒント
「自助・共助・公助」の三つをバランスよく使うことが、立ち直るためにとても大切です。ここでは、リカバリーを助けるための具体的なヒントをいくつか紹介します。
1. 自己ケアを習慣にする
毎日の生活の中で、ストレスを減らす時間を作ることが大事です。マインドフルネスや散歩など、リラックスできる活動を取り入れましょう。さらに、趣味に没頭する時間を持つこともおすすめです。絵を描いたり音楽を楽しんだりすることで、気持ちがリフレッシュされ、前向きなエネルギーを得ることができます。
2. 人とのつながりを大切にする
友達や家族と定期的に話すことや、共通の趣味を持つグループに参加することで、孤独感を減らすことができます。また、地域のイベントに参加して新しいつながりを作ることも有効です。新しい友達を作ることで、違った視点を得たり、互いに助け合う関係を築くことができます。
3. 公的支援を利用する
自分だけでは解決できない問題があるときは、福祉制度や相談窓口を利用しましょう。例えば、地域の相談センターや専門カウンセラーの力を借りることで、新しい視点や解決策を見つけることができます。また、医療機関での専門的なサポートを受けることも重要です。公的支援を受けることで、安心して生活を再構築する手助けが得られます。
4. 情報を集めて自分に合った支援を見つける
公助を受けるには、制度についての情報を正しく理解することが必要です。インターネットや自治体の窓口で、自分に合った支援制度を調べてみましょう。情報を得ることで、自分にとってどのような支援が最適かを判断しやすくなります。積極的に情報を集めることで、必要なサポートを適切に受けることができるようになります。
5. 小さな目標を立てる
リカバリーの過程では、小さな目標を立て、それを一つずつ達成していくことが大切です。例えば、毎日10分間散歩をする、週に一度友達と会う、といった小さな目標を立てることで、達成感を感じやすくなり、前向きな気持ちを保つことができます。小さな成功体験が積み重なっていくことで、自信を取り戻し、より大きな目標に挑戦する力が湧いてきます。
まとめ
「自助・共助・公助」は、それぞれが単独で機能するものではなく、互いに助け合いながら人々の生活を支える大事な仕組みです。現代の日本社会にはいろいろな課題がありますが、この三つの柱をバランスよく使うことで、困難な状況から立ち直ることができます。自分のケアを大切にし、周りの人と支え合いながら、公的な支援も利用して、誰もが安心して生活できる社会を目指していきましょう。
これからの社会では、「自助・共助・公助」の考え方をさらに広めていくことが重要です。個人が自分の力を最大限に発揮し、コミュニティが支え合い、社会全体で弱い立場の人を守ることができる仕組みを作ることで、より多くの人が安心して暮らせる未来を築いていくことができます。一人ひとりが持つ力を信じ、周囲と協力し、公的なサポートを活用して、共により良い社会を作っていきましょう。
しんしん心理研究所では、困難な状況に直面した方へのサポートを行なっています。いつでも相談にお越しください。
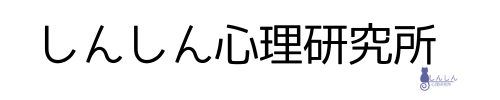
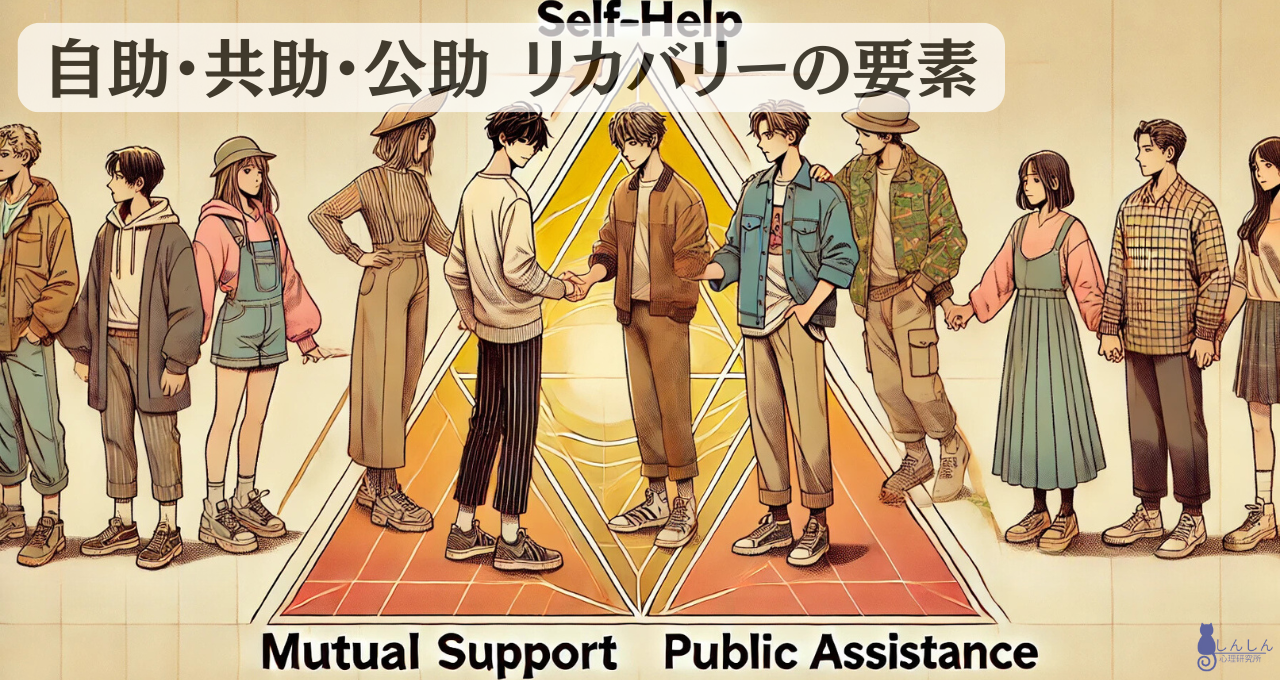

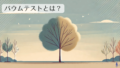
コメント